笑われるのではなく笑わせる“芸人のアーティスト化”
そもそもお笑いの世界で松本人志とは何をした人なのでしょうか? 筆者はそれを“芸人のアーティスト化”だと考えます。芸人とは客に笑われるのではなく、客を笑わせる存在である。それを明確に意識し、またそうした厳しさを隠そうとしない。お笑い芸人に技術者的なイメージを与えた、初めてのタレントだったのではないでしょうか。
では、そのような境地に至るまでの経緯をざっと振り返ってみましょう。自らのボケに気づかない観客に不満を抱き『笑っていいとも』を降板した(1989年4月-1993年3月レギュラー)のに端を発し、『ごっつええ感じ』(1991-1997 フジテレビ)終了前後からは張り詰めた緊張感が漂い出しました。
そして作務衣(さむえ)姿で大仏と向き合い自らの笑いを追求する『一人ごっつ』(1996-1997)。その間にもランダムに示される写真に一言ネタを放ち続ける伝説の武道館“言い値ライブ”『松風95』の書籍化もありました。
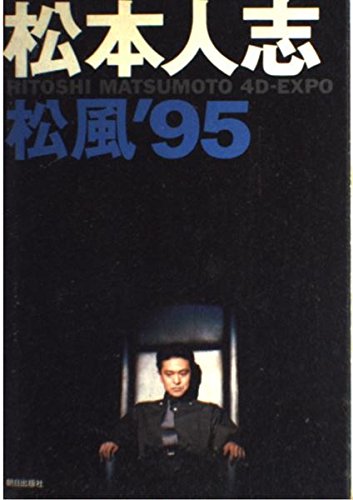
「松本人志 松風’95」朝日出版社
こうして松本は着々と実験的なお笑いの構築に努めてきたのです。どう考えても一家団欒(いっかだんらん)にそぐわない題材に笑いを求める姿は、常軌(じょうき)を逸していました。それは他ならぬ松本自身が一番強く自覚していたようです。
<もう日本人はどうしようもなくアホですね。はっきり言って、1人の賢いやつが200人くらいのアホの面倒をみてるような状態ですよ。こればっかりはしようがないです。それでも、僕のやってる笑いもそうですけど、すぐにはわかってもらえなくても今やっておかないといけないことって、やっぱりあると思うんです。たとえれば宇宙旅行の実験みたいなもんで、スペースシャトルにしたって、この10年や20年でどうなるもんでもない。僕らが生きてる間に自由に宇宙旅行ができるようにはならないでしょうけど、孫やその孫のために税金を使ってやってる。>(『シネマ坊主』著・松本人志 日経BP社刊 p.16より)

松本人志「シネマ坊主」日経BP出版センター
つまり、松本は人を笑わせる動機において、明確に自分がいる場所の高みを意識していた。“バカどもを教育してやる”という設定で笑いの論法を鍛えてきたのですね。生まれながらのカリスマであるというストーリーを補強するためにお笑いをやってきたわけです。
実際、“天才の苦悩”を本気で吐露する発言もあります。数学の天才を描いた映画『π』(ダーレン・アロノフスキー監督)を観て、松本はこうこぼすのです。
<才能に秀でた者の壊れ方というか、ボクもああいう心境によくなりますから。アホのほうが楽やなあみたいなね。なまじっか頭よく生まれてしまうと、傷つくことも多いし、イライラすることも多い。アホはストレスたまらんし、ええと思いますよ。>(『シネマ坊主』p.46より)