この過剰な屈託(くったく)の無さがぎりぎり笑いにつながっている構図を、恐らく最初に指摘したのが思想家の吉本隆明(1924-2012)でしょう。
ベストセラー『遺書』(1994年 朝日新聞出版刊)に続く『松本』(1995年 朝日新聞出版刊)にある<せっかくオレ様が笑わしてやっているのに>とか<孝行したいときに親はなしという言葉があるが、笑いたいときに松本なしにならないよう、気をつけたまえ。>という文章を引き、こう論じます。
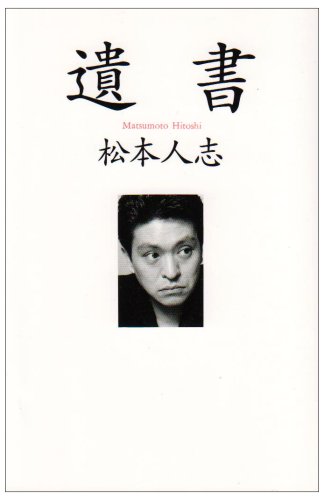
松本人志「遺書」朝日新聞出版
<おれは天才だとかおれの芸は高度なものだとか、半分はほんとにバカな天狗だが、半分はお笑いをかもしだすためのお笑い芸として、自惚れというよりも、お飾りのピラピラとして二冊の本を飾っている。こういう個所を本気で読んで感心したりする読者は、ダウンタウンのお笑い芸をみて、感心するお客とおなじだ。残念ながらこの自己妄想の誇大さを真にうけるほどダウンタウンのお笑い芸はできていない。だが可能性はもっている気がする。>(『消費のなかの芸―――ベストセラーを読む』著・吉本隆明 ロッキング・オン刊 p.301-302より)
“天才”自称にはホラ吹きと本気があいまいに混じり合っている
松本人志のカリスマ性は、こうした本気ともウソともつかぬ宙ぶらりんの真空地帯の中で肥大していき、また視聴者やファンも彼に協調して育てていった側面があるのです。
本来話芸であるはずのホラ吹きからにじみ出てしまう自我。筆者は、この芸と本性があいまいに混じり合った部分に、人々が松本人志を語りたくなってしまう理由があるのだと思います。判断がつかないからこそ、結論を導き出したくなってしまうのですね。