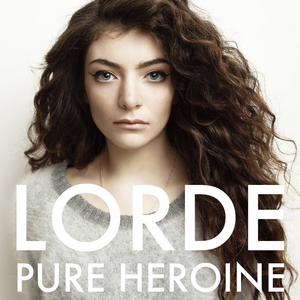
昨年後半、ニュージーランドから突如として現れた17歳の少女が、世界の音楽シーンに衝撃を与えました。本名エラ・イェリッチ・オコナー、通称Lorde(ロード)。彼女のデビューシングル『Royals』は、発売されるやいなや、瞬く間にチャートを駆け上がっていきました。
新たな才能をキャッチすることに抜かりがないエルトン・ジョンは、「レディー・ガガの進むべき道はここにある」と絶賛しました。
さらに興味深いことに、『Royals』はヒップホップチャートでも支持を広げ、主にブラックカルチャーを取り上げるMTVの『BET 106 & PARK』のような番組でも曲が流れると、オーディエンスから拍手が沸き起こるほどで、ジャンルを横断するように広がっていったのです。
●Lorde『Royals』(2014年グラミー賞、年間最優秀楽曲賞を受賞)
⇒【動画】 http://www.youtube.com/watch?v=nlcIKh6sBtc
しかし曲は、そんな周囲の熱狂とは全く対照的な色彩を帯びています。バスドラとフィンガースナップのようなサウンドを組み合わせたドラムマシンのパターンが続く他は、小節の頭に合図程度にコードチェンジを示唆するシンセベースが鳴っているのみ。
あとは、Lordeのボーカルと、サンプリングされたと思しき女性クワイヤが、ところどころ曲中のキーフレーズにハーモニーを加えるぐらいで、ヒットチャートに登場する楽曲としては、近年稀にみる音数の少なさと言っていいでしょう。
そして歌詞は、ヒットチャートを席巻しているようなパーティーチューンに対して抵抗を試みてはいるのですが、そこで使われている言葉の一つ一つが気だるいのです。かといって、たとえばベックのように文明批評を担わされている感覚からも程遠く、デフレーションが板についているのですね。
ゆえに、この禁欲的と言うのも憚られるほどの静粛な楽曲だからこそ、Lordeのメロディセンスが際立っているのだと言えます。
彼女の歌の歩み方のうちにコードがどう進展していくのかが含まれている。あるフレーズの歌い終わりに、次なる最適なハーモニーのヒントが隠されている。だからギターや鍵盤といった、いわゆる上物の助けを必要とすることなく、楽曲を構成できてしまうのです。
自身も類稀なメロディメイカーであるエルトン・ジョンは、ここに彼女の本質的な才能を嗅ぎ取ったのでしょう。
それにしても、とことん“地味”な曲をヒットさせるだけの聴き手の土壌が、欧米にはまだ残っているのですね。こういったシンガーソングライターをただ生むだけでなく、市場にあまねく流通させる、それを可能にするだけの感性が、多くの人々に備わっている。
羨ましくもありますし、まだまだ謙虚に学ばなければならないのだなと、再認識させられます。
しかし、昨年来『Royals』を何度か聴くうちに、ある日本のミュージシャンの楽曲が頭をよぎるようになったのです。Ultra Livingの『Homesick』は、1998年に発表されたアルバム『Monochromatic Adventure』からシングルカットされた曲で、当時深夜帯を中心に時折MTVでPVが流れていました。
●Ultra Living『Homesick』
⇒【動画】 http://www.youtube.com/watch?v=01WjOL4cU0c
これは『Royals』にはない、J-POP的な“泣き”のキャッチーさと、ストイックなサウンドプロダクションを際どいバランスで成立させている、日本の誇るべきポップスであります。
「カワイイ」やら「Cool」やらでお茶を濁すという怠惰が起こる前に、このような敬虔さと大胆さとを併せ持った楽曲が生まれていたのです。Lordeの出現は、そのことを思い出させてもくれました。
『Royals』はジャンルを横断し、16年という時間と国境を縦断する懐の深さを持ち合わせた一曲だと言えるでしょう。
<TEXT/石黒隆之>
石黒隆之
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter:
@TakayukiIshigu4
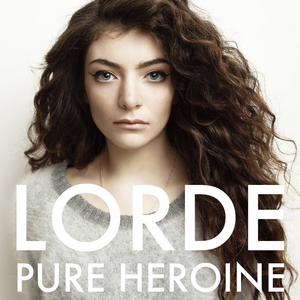 昨年後半、ニュージーランドから突如として現れた17歳の少女が、世界の音楽シーンに衝撃を与えました。本名エラ・イェリッチ・オコナー、通称Lorde(ロード)。彼女のデビューシングル『Royals』は、発売されるやいなや、瞬く間にチャートを駆け上がっていきました。
新たな才能をキャッチすることに抜かりがないエルトン・ジョンは、「レディー・ガガの進むべき道はここにある」と絶賛しました。
さらに興味深いことに、『Royals』はヒップホップチャートでも支持を広げ、主にブラックカルチャーを取り上げるMTVの『BET 106 & PARK』のような番組でも曲が流れると、オーディエンスから拍手が沸き起こるほどで、ジャンルを横断するように広がっていったのです。
昨年後半、ニュージーランドから突如として現れた17歳の少女が、世界の音楽シーンに衝撃を与えました。本名エラ・イェリッチ・オコナー、通称Lorde(ロード)。彼女のデビューシングル『Royals』は、発売されるやいなや、瞬く間にチャートを駆け上がっていきました。
新たな才能をキャッチすることに抜かりがないエルトン・ジョンは、「レディー・ガガの進むべき道はここにある」と絶賛しました。
さらに興味深いことに、『Royals』はヒップホップチャートでも支持を広げ、主にブラックカルチャーを取り上げるMTVの『BET 106 & PARK』のような番組でも曲が流れると、オーディエンスから拍手が沸き起こるほどで、ジャンルを横断するように広がっていったのです。









