お金に困って“子宮を売り渡した”貧困女性と、買った夫婦の“息が詰まるような罪悪感”。代理母出産をめぐるドラマの結末は
観れば観るほど考えさせられてしまう今期のドラマが、『燕は戻ってこない』(NHK総合、火曜よる10時~)だ。真っ向から不妊、代理母、若い女性の困窮、性と生殖の問題に取り組んでいる。原作は、桐野夏生さんの同名小説で、原作にほぼ忠実に物語は進んできた。
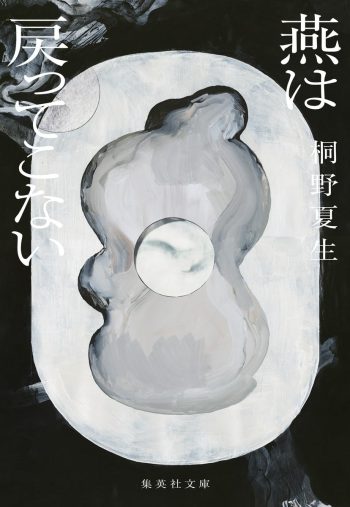 ドラマの冒頭には、毎回、「現在、第三者の女性の子宮を用いる生殖医療『代理出産』について、国内の法は整備されていない。倫理的観点から、日本産科婦人科学会では本医療を認めていない」というテロップが出る。
とにかく登場人物の誰もが「エゴの塊」なのだ、客観的に見ると。ただ、誰も悪くはない。
そして誰もが必死に生きている。だからこそ観ていて苦しくなる。
ドラマの冒頭には、毎回、「現在、第三者の女性の子宮を用いる生殖医療『代理出産』について、国内の法は整備されていない。倫理的観点から、日本産科婦人科学会では本医療を認めていない」というテロップが出る。
とにかく登場人物の誰もが「エゴの塊」なのだ、客観的に見ると。ただ、誰も悪くはない。
そして誰もが必死に生きている。だからこそ観ていて苦しくなる。
自分と息子の「特別な才能」を継いだ3代目が見たい女性。彼女は代理母出産の契約に2千万円を出すことも厭わない。息子はそんな母に同調、自分の遺伝子を継ぐ子を切望する。その妻は、産めないことへの強いコンプレックスを抱えている。代理母を頼むのは「搾取」だと非難しながら、夫の意図を翻せない。心は少しずつ夫から離れていく。そして代理母は、金のために子宮を売り渡す。
大石理紀(リキ)は、都内の病院で事務職として働く派遣員だ。古くて薄暗い病院で、朝8時から夕方5時半まで働いて手取りは14万円。日当たりの悪い格安アパートに5万8千円の家賃を支払い、残りの8万2千円で暮らしている。生まれ育った北海道で介護の仕事をしながら200万という金を貯めて、何もない場所から何でもある場所、東京へとやってきたのだが、生活は苦しく、まったくゆとりが持てずにいる。
「一度でいいからお金の心配のいらない生活がしたい」と思うほど、リキは日々、汲々としている。同じ給料でも、東京に実家がある人ならまったく違うお金の使い方ができるはず。産まれる前から、人間はすでに不公平なのだ。同僚のテルは、給料だけでは暮らしていけないと週末には風俗の仕事をしているほどだ。
そんなテルから、卵子提供のアルバイトがあると言われたのが、物語の発端だ。リキを演じているのは石橋静河。どこか投げやりな感じ、心の中をうまく言語化できず、だが自分の不満や置かれた現状を客観視できる今どきのアラサーを、ごく自然にリアルに演じている。
そして彼女は卵子提供ではなく、「代理母」への道を歩んでいく。それを依頼したのは、草桶基(稲垣吾郎)、悠子(内田有紀)夫妻。世界的バレエダンサーだった母・草桶千味子(黒木瞳)は、息子の基が悠子と不倫し、ダンサーである妻と離婚して再婚したため、悠子を快く思っていない。しかも、息子夫婦にはなかなか子どもができない。千味子は、自分と息子の遺伝子を継ぐ者の誕生を熱望している。悠子にとって義母にあたる千味子の存在感は、原作よりドラマのほうがずっと大きい。そして基も、「おかあさんと僕の遺伝子を継いだ子をバレエダンサーにしたい」と何の疑いもなく思っている。
ところが悠子は三度流産したあと、もう子どもはむずかしいと言われてしまう。だが基はあきらめきれない。そこでアメリカの生殖医療専門クリニックの日本エージェントに登録し、紹介してもらったのがリキというわけだ。
リキは1千万円という報酬をもらい、代理母になる決意を固める。とにかく今の状況から抜け出したかったのだろう。アパートの自転車置き場で、怒鳴り散らす変なオヤジにからまれ続け、節約のためランチさえまっとうに食べられない。もうじき30歳、お先真っ暗な現状から、どんな手を使っても抜け出したい。人工授精で子どもを授かれば、今の困窮生活から逃れられる。彼女はそう考えた。基と悠子は書類上、離婚し、リキは基と婚姻届を出した。子どもを産んだらすぐに離婚して、基と悠子は再度、婚姻届を出す。そういう手はずになっていた。
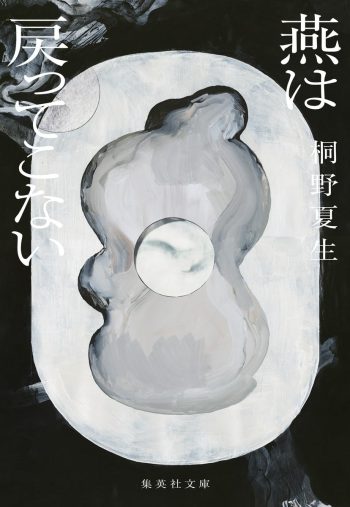
桐野夏生『燕は戻ってこない』(集英社文庫)















