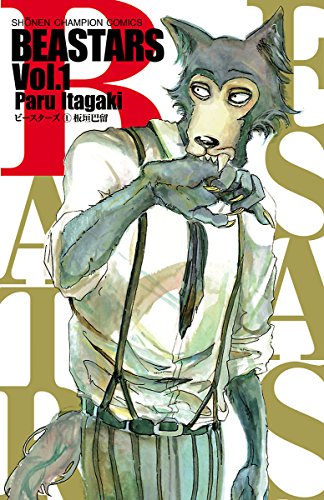「きみを愛している。」
歌や映画や小説の中にあるその言葉が、現実より自分より、信じられることがある。厳密には、人は、愛のためにすべての人生を、燃やすことなどできないのかもしれない。けれど、愛を描くため生まれた作品たちに触れたならば、その向こう側にあるものを、一瞬、目にすることができるかもしれない。作品ごしに触れた、愛について。この連載では、書いていきたい。
歪みの中でしか、生きられない。――板垣巴留『BEASTARS』について
『BEASTARS』は、多種多様な動物たちが同じ言語で語り合い、学校や会社や警察や裏世界のある社会に生きる物語だ。草食動物と肉食動物が肩を並べ、授業を受ける。だから、「肉を食べる」という行為は重罪として扱われている。けれど、「肉を食べる」というのは肉食動物にとって贅沢でも、娯楽でもなく、ただ「生きるため」。物語のなかで、肉の代用品として大豆や卵が登場する。それでも生きていくことはできるからと、肉への欲は「持つべきではないもの」して扱われる。けれど、彼らは生きている限り、肉を欲する自らの内臓を抱き続けるしかない。また、肉を食べることで自らの力を高めたり、雑念を消すことができる、という描写もあり、彼らは肉を食べないことで確かに弱体化し、枯れ果てた泉のようなものを心に持つ。肉を欲することのない肉食動物こそが、美しいとされ、優しく繊細とされ、欲求に負けること、開き直ることが愚かさとされる。それは歪みにもみえる。そして、この歪みを生んだのは、他でもない「言葉」なんだ。
共通の言葉を用いる、すぐそばに暮らしていて、当たり前のように交流する。肉を食べるチャンスを得た肉食動物が、友達の草食動物のことを思い出し、口にすることができなかったというシーンがある。彼らを縛っているのはけっして「決まり」なんかではなく、彼ら自身の「良心」だ。友人の笑顔、共に過ごした時間。それらが彼らの足かせとなる。罪の意識が彼らの「食肉」を「罪」と確定させている。彼らはだから息苦しく、孤独を感じる。単なる「肉を奪われた肉食動物」ではなく、彼らは、別のものを手にしており、だからこそ苦しい。そしてこの物語が素晴らしいのは、そうした彼らを救うのもまた、彼らの「良心」であると、はっきりと描いていることだろう。
苦しむたびに思う、この歪みをどうすれば正すことができるのだろう。けれど「苦しみを取り除く」ということが、イコール「幸福を呼び起こす」とも言えない。彼らは苦しみながらも、関わり合い、語り合い続ける。現実における動物たちを知っていれば、つい、「そこまでしてどうして共存するのか」と思ってしまう。コミュニケーションをとるのではなく、サファリを駆け回る動物たちを「真のあるべき姿」と捉えてしまう。けれど、共存をやめる、というのは最適解に見えて、実はただの逃避でしかない。なにひとつ解決はせず、新たな幸福も望めない。ただ、何もかもを失うだけだ。
痛みに苦しむとき、その原因が最初からなければよかったと願いながら、どこかでそうではないとわかってしまうことがある。それらが自らの体に、人生に、深く突き刺さって、もはやそれらとともに生きてきたこと。自分の、人生の一部となっていること。ただ、痛みを生むだけではないのだと知ってしまうことが。
彼らは傷つき、欲望を押さえ込みながらも、それでも関わり合う、自らの良心を貫くように。だから、そこで「愛」という言葉が登場するのだ。愛こそが異種族を結びつけるのだと、この物語は結論づけている。
肉を食べたがる本能と、それに抗う自らの良心。肉体として「食べる」ことは自然であるのに、それを「罪」と社会も自分もみなしている。冒頭で「歪み」と書いたそれは、本当は「歪み」という言葉では足りないものだ。彼らが「愛」にいきつくとき、そこにもまたその「歪み」は大きく関わっているのだから。
生きることは、歪んでいくこと。自分と他者の間にある絶対的な「違い」を、埋めたいと望んだり、尊重してくれと願ったり。けれどどうあがいても「分かり合えない」、そしてその「分かり合えなさ」すら完全には尊重できないという事実が、心の奥、社会の奥、あのひとの奥に、横たわっている。生きるたびにそのことを思い出し、けれど願いも欲望も、生きるたびにまた、深まっていく。「歪み」が苦しさを生む、けれど、「歪み」がなければ生きていけない、生きていく意味を自分は見出せないのかもしれないと、つい、考えてしまう。そんなこと絶対に、思いたくない、思いたくもないんだ。
この物語は、「人間」の話ではない。人間の比喩として動物を描くのではなく、あくまで、動物は「動物」として描かれる。だから「食肉」という罪を、人間の行為と重ねて捉えることは難しく、その「わからなさ」はけれど、彼らが「愛」に行き着くその様をより鮮烈に見せてくれる。
彼らには共感などほとんどできない。肉食動物と日々を過ごす草食動物の恐怖、肉への欲求が沸き起こる肉食動物の不安、そうして互いを「友」として見つめてるという点。想像はできる、けれど想像ができるというだけで「わかる」と言ってしまいたくはない、そんな彼らの感情を踏みにじることはしたくない。そうしてなによりも、彼らが抱く感情や、友情を、それでも読み手は信じることができるから、それでいいと思っている。あの子があの子を信じること、あの子があの子に友情を感じること。それは信じられる、それだけで十分だと思えるなら。もう。
この鮮烈さは、本来は人間同士でも、人間を描く物語でも、あるはずのものだった。他人を目の前にすると、その肌の感じとか、目の光とか、そういう情報量に圧倒されて、彼らが自分のわかりようのない人生を経てここにいるのだということを思い知る。だから、一瞬その人の感情を、心から信じられるときがきたなら、忘れられない感覚となるだろう。そうして、人間の物語でも。よくありそうなシチュエーション、見たことのある人物の組み合わせ、そういうものをとっかかりに、キャラクターの気持ちを想像し、わかることができたと思う。でも、本当は、物語もまた、わからない存在に対して、「わからないけれど、でも君がそう思った、そのことだけは信じられる」と思える瞬間が重要なのだろう。動物同士の、「捕食」というテーマでの関わり合い、その果てにある「愛」に行き着いた時、この鮮烈さ、眩しさを初めて目にした時のように、思い出していた。
歪みなどいらないんだ、ただ静かに暮らしたいし、もう誰とも会わずに眠り続けたいとすら、思うことは何度もある。それを否定などできないし、たとえ信じられる喜びに出会えたとしても、それらは変わらない。歪みは苦しみだって生み続ける。たとえすばらしいものを生んでくれたとしても。そのすばらしいものが、苦しみを埋めてくれるわけでもないんだ。
ただ歪みの中で、歪みがあるからこそ生じる「愛」に出会うとき、「歪みなんかいらなかった」と叫びたくなる内臓が、そっと撫でられたように感じるのかもしれない。本当にそうだ、歪みがなければ傷つくことなどないのだし。けれど、でも、ここに愛がある。叫びながら望んだ「ありえないほど漂白された世界」とはまったく違う、その物語に、愛に行き着いた物語に、惹きつけられる。私はまだ、この世界で生きようとしているのだと、気付くんだ。
 『BEASTARS(ビースターズ)』板垣巴留:著
『BEASTARS(ビースターズ)』板垣巴留:著
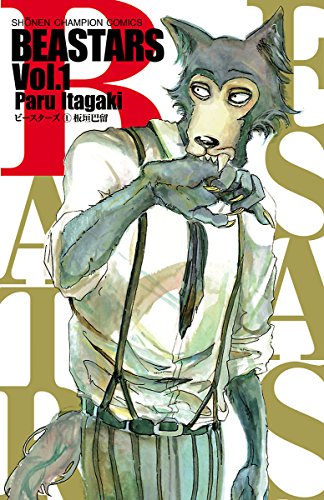
秋田書店
<文/最果タヒ イラスト/とんぼせんせい>
 「きみを愛している。」
歌や映画や小説の中にあるその言葉が、現実より自分より、信じられることがある。厳密には、人は、愛のためにすべての人生を、燃やすことなどできないのかもしれない。けれど、愛を描くため生まれた作品たちに触れたならば、その向こう側にあるものを、一瞬、目にすることができるかもしれない。作品ごしに触れた、愛について。この連載では、書いていきたい。
「きみを愛している。」
歌や映画や小説の中にあるその言葉が、現実より自分より、信じられることがある。厳密には、人は、愛のためにすべての人生を、燃やすことなどできないのかもしれない。けれど、愛を描くため生まれた作品たちに触れたならば、その向こう側にあるものを、一瞬、目にすることができるかもしれない。作品ごしに触れた、愛について。この連載では、書いていきたい。
 『BEASTARS(ビースターズ)』板垣巴留:著
<文/最果タヒ イラスト/とんぼせんせい>
『BEASTARS(ビースターズ)』板垣巴留:著
<文/最果タヒ イラスト/とんぼせんせい>