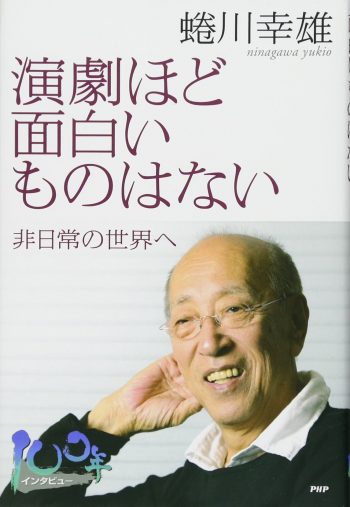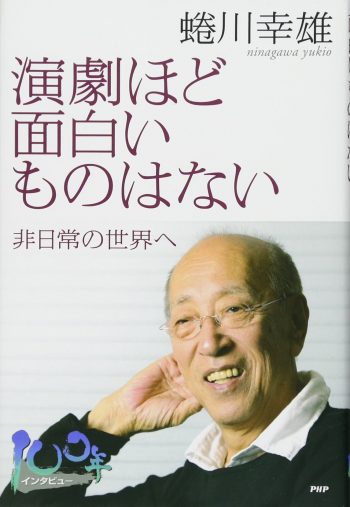
蜷川幸雄「演劇ほど面白いものはない 非日常の世界へ」PHP研究所
これはご本人が長らく気にしていたことであり、世の中の人に嫉妬を覚えさせる点である。
蜷川実花の父は世界的な演出家・蜷川幸雄で、写真家としてデビューしたとき、そのことを伏せていたそうだが、なかなかない名前なので、なんとなく関係があることが周知されてしまい、そうすると、“親の七光り”に違いないと思われてしまう。常にバイアスをかけて見られ、本人の本質を見てもらえない、二世によくある悩みである。
蜷川幸雄が2016年に亡くなってからは、そのバイアスがなくなって、いまや蜷川といえば「蜷川実花」の時代がやってきたかと思ったら、「DINER」で藤原竜也、「人間失格」で小栗旬と蜷川幸雄組の一員だった俳優を主役にして、蜷川幸雄の演出方法のオマージュもふんだんに行うという特権を駆使していた。これは追悼および魂の引き継ぎという美しい意味も当然あるはずだが、やっぱり蜷川幸雄の威光を着ているとも思ってしまう人はいるのである。
ネトフリは園子温(「愛なき森で叫べ」)や武正晴(「全裸監督」)などキネマ旬報など専門誌でも評価されるような、いわゆる映画畑の作家が参加していて、映画がなかなか自由に作れない時代、チャンスのない映画作家にもチャンスを与えてほしいと願う人も多いなか、そこそこ観客が入るが映画としてあまり評価が得られていない蜷川実花が作品を撮れてしまうという状況が面白くない人って少なくない気がする。
映画に限らず、テレビドラマも、医療ものと刑事ものとイケメンものしかつくれず鬱々としたプロデューサーやディレクターもいるはずで、蜷川実花は写真だけ撮っておけ、東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会理事として働いておけ、と思う人もいるのはわからなくはない。
私も昔、演劇ライターやりながら映画の仕事をしていたら、「演劇だけやってろ」と映画ライターのひとたちにすごく虐(いじ)められたことがある。ヒトは自分の領域を脅かす、よそ者には冷たいのである。
「FOLLOWERS」は物欲、性欲、名誉欲……とあらゆる欲望が描かれていて、それがいま不況にあえぐ日本に不似合いではないかという不満が募る。しかもこれだけ多くの欲望を描きながら、文化や教養などへの知識欲がまったく見当たらないのである。
「FOLLOWERS」で唯一の文化はタランティーノ。でもそこに愛があるとはあまり思えない。弁の立つ人たちが蜷川実花を批判したがる理由は、このように共通の文化体験が作品のなかに見つけられないところが最も大きいのではないだろうか。かろうじて、安野モヨコや岡崎京子、太宰治と原作者の文脈から何かを語ることができるのだが、蜷川実花の作風の文脈がみつからない。
とりわけオリジナルの「FOLLOWERS」には何もない。ここまで空っぽにするほうが逆に才能のような気がするのだが、語りたい人にとっては寄る辺がないのである。