
歌や映画や小説の中にあるその言葉が、現実より自分より、信じられることがある。厳密には、人は、愛のためにすべての人生を、燃やすことなどできないのかもしれない。けれど、愛を描くため生まれた作品たちに触れたならば、その向こう側にあるものを、一瞬、目にすることができるかもしれない。作品ごしに触れた、愛について。この連載では、書いていきたい。
私は本当に、主人公としての、もしくは物語のトリックスターとしての、狂気や勇気を持つことができない登場人物が好きだ。そうした人が友や敵や恋人に閃光のような心の持ち主がいるがために、巻き込まれ、感情が止めどなく変わり、隕石のように燃えながら生きる姿を愛している。それは、人が自らの人生を思うときに見る風景そのもので、多くの人にとって(少なくとも私にとって)、自分はどこまでもそんな、受け身の凡庸な隕石であり、そのことにめちゃくちゃに傷つきながらも、でも本当はそれだけではなく、誰かにとっては自分もまた「閃光」だったのだと見せてくれるのが、こうした物語の人物だからだろう。
「ロミオとジュリエット」のベンヴォーリオはまさにそういう人です。原作だと彼はそこまで多く描写された人物ではないけれど、ミュージカル作品「ロミオとジュリエット」におけるベンヴォーリオは、「友達」こそが与えられた最重要の設定で、つまり、彼自身の性質ではなく、他者との関係性が彼の設定の軸にある。今回の宝塚星組公演では瀬央さんと綺城さんが役替わりで演じていますが、どちらも完全に違うベンヴォーリオになっていて、なによりベンヴォーリオの感情の動きや流れそのものが違っているのがすごく見応えがあって好きでした。友人という立場こそが彼の固定された設定であり、そこからどう肉付けされるのかは演者さんによってだいぶ違っていて、この「関係性が肉付けの中心にある」というのが、コミュニケーションとしての芝居がより極まるトリガーになっていて、ベンヴォーリオについては特に、彼個人について考えるより観る人はその周囲の役の演者さん込みで考えた方がよりおもしろく、どちらもそのときのメンバーだからこその演じ方になっていてそこが素晴らしいなと思います。
「ロミオとジュリエット」を、許されない恋に落ちた二人が死んでしまう物語だとは知っていても、実は全編を見たことはなく、ティボルト・マキューシオ・ベンヴォーリオを知らない、という人もそれなりにいると思うので少しだけここで紹介をしておきます。ロミオのモンタギュー家と、ジュリエットのキャピュレット家は何代にもわたり対立しており、彼らの住むヴェローナという街には憎しみの感情が満ち満ちています。マキューシオとベンヴォーリオはモンタギュー側の青年。ティボルトはジュリエットのいとこで、キャピュレットの後継でもあります。マキューシオとベンヴォーリオは、二人でモンタギューの若者たちを率いるリーダーであり、片割れのマキューシオは大公の親戚でかなり良い家柄ですが、本人はそこから逃れるように喧嘩に明け暮れ、また、享楽的な日々を送っています。一方のベンヴォーリオはロミオのいとこで、ロミオの世話を頼まれていることからも、モンタギュー家からは非常に信頼されていることが窺えます。彼は、ロミオとマキューシオの昔からの友人で、争いを好まないマイペースなロミオを見守り、血の気の多いマキューシオの悪巧みに友達らしく賛同しながらも、彼の彼自身や仲間を傷つけかねない暴走はきちんと諌めるような、そんな「兄」のような人物です。
今回は星組「ロミオとジュリエット」(2021)のB日程で綺城ひか理さんが演じたベンヴォーリオについて書こうと思います。
ロミオ(礼真琴さん)は争いを好まず、両家の対立とも距離を置き、ひたすらに恋に憧れる青年ではありますが、それゆえに恋の相手に出会ったときの並外れた行動力と周囲の見えなさは苛烈で、対立・血・憎しみに満ちたヴェローナという街において純粋であり続けることがどれほどの強さによって成し遂げられていたのかが、物語が進むごとに明らかになり、主人公としての、芯が通り過ぎたもはや恐ろしいほどの煌めきが物語を突き動かしていきます。そしてマキューシオ(天華えまさん)は、若者たちのリーダーであり三人の中で一番喧嘩っぱやく、しかし非常に仲間思いでもあり、街の狂った状態に大人たちのように鈍感になることはできず、街の狂気をあえて楽しむことで自分なりの青春を生きる人物です。作中で、敵のキャピュレット家の仮面舞踏会に忍び込み、パーティをめちゃくちゃにすることを彼が提案しますが、憎しみの中で生きるしかないからこそ、その中で仲間達と享楽的であることを選択するという、そんな脆さのある若者。この二人の間に立つのが、「友人」ベンヴォーリオなのです。
純真さゆえの苛烈さをもつロミオと、素直であるがために運命を拒むことができず現実に染まってしまったマキューシオと違って、ベンヴォーリオは「二人の友人である」ということが何よりも重要な人物設定となっていて、2人ほど突出した性質は持っていません。ただ、ベンヴォーリオがいるからこそ彼らは友人関係を持つし、彼らの「友情」そのものがベンヴォーリオとして現れている、とも言えます。この「友情」のありかたが、生々しくて現実的で、でもとても優しく、未完成なまま成熟していて、だからこそ悲しく、そのことについて今日は書きたいのです。強烈な人物たちを一つの空間にまとめるためにいるバランサーのようでもあるけれど、実際のところ、一番人として生々しい部分を担うのも、きっとベンヴォーリオだった。
友人というのは奇妙な関係で、ロミオが「恋人」ジュリエットについて、命を賭けて守らなくてはならないと語り、実際彼女のために命を捨ててしまうのだけれど、逆にそうなり得ないのが「友人」で、命なんて賭けることはない相手であり、でも、もし敵に友が殺されたら咄嗟にその敵に復讐してしまうような、そんな対象でもあります。決して愛に友情が劣るという話ではなく、友人との愛は、どこまでも二人を一つにせず、運命共同体になどせず、そしてそのことが当事者を支えるし、「個人であること」に誇りをもたらす。だからこそ介入できない部分があって、どれほど友達であっても止められず、引き止めるチャンスも得られずに、落ちていく友人の背中を見るしかないこともある。その悔いや悲しみから復讐や絶望に飲まれてしまうこともあるし、それは友人関係の限界だとか、無力さではなくて、その関わりきれないことこそが、友情の、そして他者を友と思うことの美しさでもある。
ジュリエットが死んでしまったその日、ベンヴォーリオはロミオにジュリエットの死を伝えたあと、「一人にしてくれ」と言われ、ロミオが絶望するその姿を見ても、何も言えずにそのまま立ち去った。だから一人になったロミオは毒を手に入れ、彼女の後を追うことを決意してしまうのだけれど、これはベンヴォーリオの無力さでも、過ちでもなかったと私は思う。ベンヴォーリオは友達だからこそ、伝える以外にできることはなかったし、ロミオが立ち直ることを信じた……というより、信じるしかなかったのではないかと思うのです。
ベンヴォーリオはマキューシオほどの享楽的な面は持たないにしても、街にある狂気については染まりきっていたし、モンタギュー側のリーダーとして対立を煽り続けていたと感じます。「世界の王」はロミオとマキューシオ、ベンヴォーリオの、未来と自己を無限に信じられた青春を感じる明るい楽曲ですが、敵の家の仮面舞踏会に忍び込みパーティーをめちゃくちゃにしよう、とマキューシオが提案する「マブの女王」もまた、その曲と、そこに仕込まれた悪意を楽しげに踊るベンヴォーリオを見ていると、「湿度高めの青春の歌」なのだと思う。友と悪いことをするのは楽しく、それでしか燃やせない青春はある。生まれた時から敵がいて、相手の血が流れても憐れむより喜びが湧いてこなくちゃ生きていけないような街で、彼らが「楽しく」「友と」生きるために、そうした青春はあって当たり前だとさえ感じます。
友人や仲間に対して見せる顔は優しくても、その優しさがロミオのような絶対的なものではなく、不平等で、相対的で、身勝手で、根っこにはたぶん幼さもあった。つまり、「友達だから、仲間だから、優しくしたい」と思うような、幼い心が抱くような優しさこそが貫かれ、それらが平等さや正義に変容することはないまま成熟し(しかしそれはほとんどの人間がそうです)、「器の大きなベンヴォーリオ」が作り出されていたのでは、と思うのです。
ベンヴォーリオは、絶望するロミオを置いて立ち去る時も、ロミオの追放が決まってその場から立ち去る時も、見たことがないぐらい幼い顔で走り去ります。できるだけ周りを見て、他者に気を配っているベンヴォーリオはそこにはいなくて、でもここにはとても一貫性を感じるのです。
絶望する友に何も言えなかったベンヴォーリオ。これが、ロミオだったら違ったかもしれない。マキューシオがティボルトに殺された時、復讐のために即座に走り出したロミオと、それを目で追うしかできなかったベンヴォーリオは真逆だった。ベンヴォーリオは他者を思い、思いやることで、超えることのできない距離を自分と相手の間に見出してしまう人だ。それは無邪気なロミオの、愛と同義の優しさとは違うけれど、その世界に生きて、現実とともにあり続けるしかない仲間たちの、生々しい「人生」を思いやるなら、自然な選択でもあるだろう。ヴェローナの街に生きる若者たちには、無邪気なだけでは、善的な選択をとっていれば、幸せになれるような人生がない。だから間違っていることを選択するしかないとき、それを否定しないのがベンヴォーリオで。たとえばマキューシオの選択は多くが間違いの中にあるが、けれどあの世界に生まれ落ちた彼に無闇に「正しく生きろ」と言うのは暴力的すぎる。彼と対になっているベンヴォーリオは、天使のような強く美しいロミオとは違って、人間としての割り切れないところを、禍々しさを許す優しさがある。それは、見方を変えればヴェローナという街に満ちた狂気を受け入れること、妥協することにもつながるし、俯瞰して見れば彼の許しは、マキューシオや仲間を救うことにはならないのかもしれない。そして彼のどこまでも関係性に依拠する優しさは、不平等だし、そして理不尽な面を持つことにもなるだろう。(敵のティボルトに対してだけ見せる強烈な冷たさは、そうした理不尽さから来ていると思う。)
ロミオの言葉がベンヴォーリオの心を打つように、彼の優しさは完璧なものではなく、理想的でも正しくもなく、ベンヴォーリオの優しさは街の良心のようだけど、街が作り出した歪みの一つでもあるんじゃないか。ただそういうものの方が、その歪みの中で生きていく人たちには必要であったり慰めであることも多く、正しさだけで息ができる世界なんてヴェローナの外にだって無い。だからこそベンヴォーリオはその優しさを育て、そうしてリーダーとして成熟していったのだと思う。
他者を尊重し、他者の、過ちも多いであろう人生をそれでも信じ、委ねるという彼の態度は、この物語においてはことごとく功を奏しません。きっと物語より以前の、モンタギューの若者たちの日常の中では、この態度はとても良い潤滑剤になっていただろうに、動き出した物語においては、何もかもが悪い方へ傾くトリガーとなってしまった。友に委ねられ、信じてもらえたとしても、ロミオがそれでも絶望するならそれはそれでロミオの個人としての自由であり、それを否定することはどうやってもできない。頑なで、自らの心に正直すぎるロミオには、現実と折り合いをつけながら生きる人々に向けられ続けたベンヴォーリオの優しさは慰めにはならなかった。そしてそれがわかっていたとしても、それでも他に方法を持つことができなかったからこそ、ベンヴォーリオは子供のような顔で走り去っていった。
ロミオ、ベンヴォーリオ、マキューシオの関係は、とても幼馴染らしい、というか(実際そうです)、小さな頃からそばにいて、それが当たり前で、近くにいたからこそ親しくなった、というのがいやというほどわかるものでした。その人の内面や能力が、友情の理由になっていない。どんな人間か、気が合うか、価値観が同じか、ということが関係ないところから友情や優しさがはじまっていて、だからこそベンヴォーリオの優しさが、ロミオとマキューシオという全く異なる性質の2人の間に立ち、三人の間にある「友情」を描いていたのだろうなと思う。
綺城さんによるベンヴォーリオの歌声は、彼の優しさや友情の起点としてある、生の感受性というか、人間っぽい幼い感性まで曝け出されていくような感じがして、それが私は好きでした。ベンヴォーリオは幼さとは無縁なぐらい、自分を律していると思いますが(不良ではあるものの)、それでも起点にある優しさが、ロミオほど教科書的な、聖なるものではなかったことも確かです。子供っぽい「友達だから、仲間だから、優しく」という感覚は、たぶん歳を重ねるにつれ、仲間を持つにつれ、友人がそれぞれ別方向に成長していくにつれ、歪みを持ったまま、成長をし続けてきたのだと思う。友達だからこそ言えないことがあり、友達だからこそ止められないことがあり、相手のそれぞれの選択を尊重し続けることはきっと負担が大きいはずで、それをそれでも繰り返してきた彼は、ロミオのようなまっさらな強靭すぎる正しい優しさではないものの、一つの成熟した人間らしい優しさを持っていたのだと感じます。
そして、成熟した人間が幸福になれるわけではない。他者を尊重してもその他者がそのまま不幸に突き進むこともある。ベンヴォーリオはどうして幸せになれないんだろう、と観劇するといつも思いますが、(好きに生きて死んでしまう子たちも悲しいが、彼らが好きに生きられるように願ってきたようなベンヴォーリオが幸せでないのが私は一番辛い)、幸せになるために必要なものなんてない、というのはよく考えれば当たり前で、置き去りにされ、何もかもを失うのがベンヴォーリオである、というのはこの物語にとってむしろとても王道で、嫌というほど真っ当であるようにも思う。何より、信じることや委ねることが彼にとって平気なものでは決してないことが、肌に突き刺さるようにわかるのが、この物語でベンヴォーリオを追う本当の良さだとも思います。
ベンヴォーリオのような人物を、生身の人間が演じることで、彼の優しさや妥協が、単なる不完全さではなく「そうしか生きられない」人間らしさに変えられていく。たとえ、不完全であっても、ベンヴォーリオほど優しさを貫ける人はそういないはずで、それなのにベンヴォーリオを観ると、自分と地続きの人間だと思えてならない。ロミオはヒーローで天使で正義であるのかもしれませんが、つまりとても非現実的な良心であり、現実を生きる人間にとっては優しさというより厳しさに見えることも多いでしょう(ロミオ自身、その厳しさを抱えきれずに、刹那的な復讐に手を染めてしまいます)。ベンヴォーリオの優しさは人間臭くて、妥協も多く、間違いもきっと多く起こします。そしてその歪みは、彼自身が選んだものとも言い難い。ベンヴォーリオがロミオを尊重するのも、マキューシオを受け止めていくのも、彼が意図的にそうしたというよりは、生きていくために自然とそうなっていったのだろうなと思うのです。ティボルトに冷たすぎることも、暴力や悪意をおもしろがってしまうことも。正論や0か1かみたいな話ではないところで、彼はやるべきことをやってきたからこそ優しく、そして環境の影響をどうやっても受け続けてしまった。両家の対立が日常で、憎しみ合うことが当たり前だったヴェローナに生まれたベンヴォーリオは、街を受け入れ、それでも友や仲間を愛したからこそ、彼の優しさは生っぽく、妥協にまみれ、観ている側の現実にまで肉薄し、現実的な日々を生きる人にとって「見覚え」のある優しさに映っていた。そして、そんな彼の優しさこそが街の「狂気」を証明するし、彼もまた一人の小さな子供で、ヴェローナという街の被害者であったことを見ている側に証明するのです。
他者の心情を汲み取ってしまう、絶対的な優しさではなく、相手を見て、その相手に対してコミュニケーションとして見せる優しさは相対的で、環境や背景に対して徹底的に正しくあることはできなくなっていく。でも、周りの人から、近しい人から、自分ができる範囲で優しくしていきたいと願う人間にとっては、そちらの優しさこそが「優しさ」で、人が人とともに生きる限り、それがたとえ危ういものだとしても、否定できないものなのです。ベンヴォーリオの優しさに、見る人が惹きつけられる時、どうしても見る側にある「優しさ」そのものや、それに対する意識が浮き彫りになる。善良な部分の自分、天使のようにはなれないけどそれでも捨てられない善性、身勝手な方法で、言葉で、他者を気遣ってしまった過去が、ベンヴォーリオに共鳴して、そうして彼の幸福を願わずにはいられなくなるのです。
性善説うんぬんは置いておくにしても、ひとは、いや、私は、昔はもっとそれなりに優しかったはずだ、と思う。それは他者にとる態度の選択肢が今よりもずっと少なくて、だから「優しくする」ということが、割合として大きく占めていたからなのかもしれない。他者に願うことが少ない分、優しくしたい、ということをもっと頻繁に思っていたし、他者に優しくすれば誰かが褒めてくれて、優しさがいつも掬い上げられていた。そういう時代を生きたことのある人にとって、誰かが優しいとき、その優しさを見るだけでとても切ない気持ちになる。優しさがどれほど儚いものか、優しさを貫くことがどれほど苦痛を伴うか、そして優しさにも身勝手さがあること、一度でも誰かに優しくして、優しいね、ありがとうね、と言われたことがある人なら、きっとよく知っている。
ベンヴォーリオは優しさを関係性の中から作り出すからこそ、仲間の変化や、仲間の痛みや怒りや負の感情を察してしまうし、それを切り捨てることができない。他者として尊重しながらも、リーダーとして、友達として、その人の痛みを無視できず、自業自得だなんてもちろん言えず、共鳴し傷つくのだろう。手を取って自分が正しいと思う道に歩ませることはできないし、決してそんなことをしようとしないのに、委ね信頼した人が、道を踏み外し落ちていくとき、彼はそれを苦しいと思うのだ。
「どうやって伝えよう」というベンヴォーリオのソロナンバーがあり、ジュリエットの死を伝えに行く、その決意のために歌われる曲。綺城さんのこの歌が素晴らしくて、それはベンヴォーリオの本当に生身の部分、子供の頃にあった、自然な優しさのところまで見えてくるような気がするから。正しくない人の優しさは偽物なんだろうか。ベンヴォーリオの役割としての「友情」や「優しさ」が、一人の人間の、見ている人たちにも地続きにあるものとして見えてきて、正しくなんてなれない場所で生きても、せめてあの人には、あの子には、優しくありたいと思い続けてしまう人に、強く響いていく声。正しくなくても、優しさは、優しさであるはずです。
視野の広い、穏やかなリーダーとして振る舞い続けた彼は、けれどこの世界を変えようとした青年ではなかった。ヴェローナという世界そのものによって殺された子供たちを前にすれば、彼の優しさも真っ当さも、彼には幸福をもたらさない。私はベンヴォーリオに、正しくあるべきだった、正しくあれと仲間達に言うべきだった、なんてことは絶対に思いたくないし、彼の優しさを罪として捉えることはしたくない。ベンヴォーリオは生き残ったけれど、彼の、彼の仲間たちを確かに救い、幸福ももたらしてきたであろう優しさは、彼にとって最も許せないものに変貌してしまったことが悲しいから。だから私は、彼に罪があるなんて、絶対に書きたくないのだ。
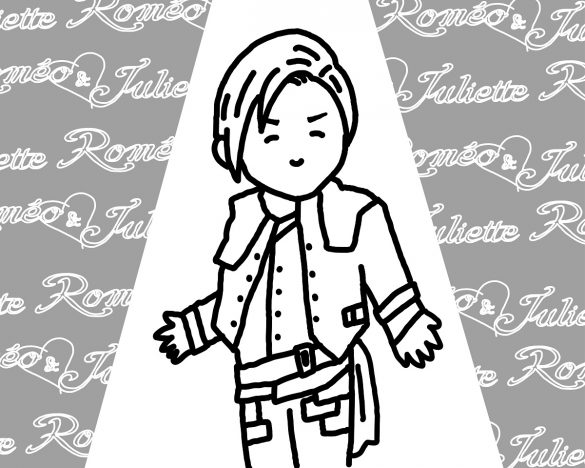
宝塚歌劇 星組公演「ロミオとジュリエット」(B日程)

『星組宝塚大劇場公演 ロミオとジュリエット』(B日程版)ブルーレイ(宝塚クリエイティブアーツ)
ミュージカル「ロミオとジュリエット」は、2010年から宝塚歌劇団にて繰り返し上演されてきました。今公演では、2013年の新人公演でロミオを演じた礼真琴さんが、星組トップスターとして再びロミオを演じました。礼真琴さんによるロミオと、舞空瞳さんによるジュリエットは、生まれた時から恋に落ちることが決まっていたことが、舞台で一目見た時から客席にもわかる、そんな鮮烈としか言いようがない「運命」を抱えた作品です。2021年の星組公演はA日程・B日程に分かれ、主要な登場人物が役替わりで演じられました。この原稿はB日程について書かれたものです。
<文/最果タヒ イラスト/とんぼせんせい>
 歌や映画や小説の中にあるその言葉が、現実より自分より、信じられることがある。厳密には、人は、愛のためにすべての人生を、燃やすことなどできないのかもしれない。けれど、愛を描くため生まれた作品たちに触れたならば、その向こう側にあるものを、一瞬、目にすることができるかもしれない。作品ごしに触れた、愛について。この連載では、書いていきたい。
歌や映画や小説の中にあるその言葉が、現実より自分より、信じられることがある。厳密には、人は、愛のためにすべての人生を、燃やすことなどできないのかもしれない。けれど、愛を描くため生まれた作品たちに触れたならば、その向こう側にあるものを、一瞬、目にすることができるかもしれない。作品ごしに触れた、愛について。この連載では、書いていきたい。
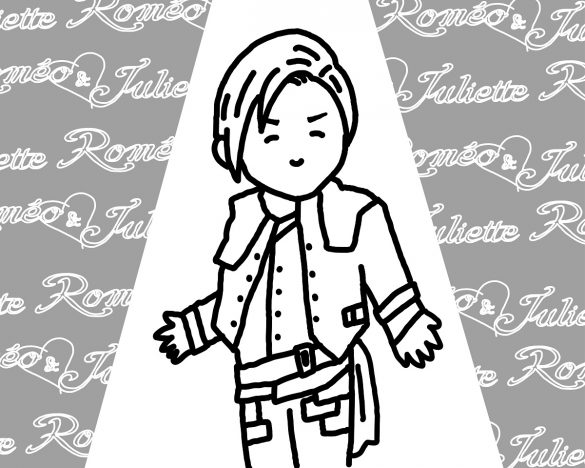 宝塚歌劇 星組公演「ロミオとジュリエット」(B日程)
ミュージカル「ロミオとジュリエット」は、2010年から宝塚歌劇団にて繰り返し上演されてきました。今公演では、2013年の新人公演でロミオを演じた礼真琴さんが、星組トップスターとして再びロミオを演じました。礼真琴さんによるロミオと、舞空瞳さんによるジュリエットは、生まれた時から恋に落ちることが決まっていたことが、舞台で一目見た時から客席にもわかる、そんな鮮烈としか言いようがない「運命」を抱えた作品です。2021年の星組公演はA日程・B日程に分かれ、主要な登場人物が役替わりで演じられました。この原稿はB日程について書かれたものです。
<文/最果タヒ イラスト/とんぼせんせい>
宝塚歌劇 星組公演「ロミオとジュリエット」(B日程)
ミュージカル「ロミオとジュリエット」は、2010年から宝塚歌劇団にて繰り返し上演されてきました。今公演では、2013年の新人公演でロミオを演じた礼真琴さんが、星組トップスターとして再びロミオを演じました。礼真琴さんによるロミオと、舞空瞳さんによるジュリエットは、生まれた時から恋に落ちることが決まっていたことが、舞台で一目見た時から客席にもわかる、そんな鮮烈としか言いようがない「運命」を抱えた作品です。2021年の星組公演はA日程・B日程に分かれ、主要な登場人物が役替わりで演じられました。この原稿はB日程について書かれたものです。
<文/最果タヒ イラスト/とんぼせんせい>















