小学校で教わった「ぞうきんがけ」は病気のモト?正しい掃除をプロに聞いた
だんだん暖かくなってきましたが、年末大掃除で片付けた部屋はキープできていますか? 「まめに掃除しているのに、気づくとホコリがたまっていて……」という人も多いのでは?
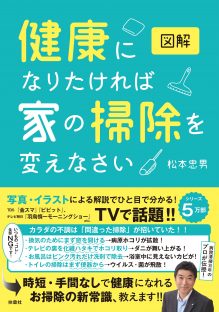 そこで、前回掃除の基本や大掃除のポイントについて語っていただいた、日本ヘルスケアクリーニング協会代表理事で、『図解 健康になりたければ家の掃除を変えなさい』(扶桑社)の著者でもある松本忠男さんに、きれいを維持する秘訣を伺いました。
そこで、前回掃除の基本や大掃除のポイントについて語っていただいた、日本ヘルスケアクリーニング協会代表理事で、『図解 健康になりたければ家の掃除を変えなさい』(扶桑社)の著者でもある松本忠男さんに、きれいを維持する秘訣を伺いました。
――前回、部屋をきれいにする方法をお話いただきましたが、きれいな状態を保つにはどうしたらいいですか?
松本忠男さん(以下、松本)「“全部をきちんとやらなきゃいけない”という思い込みや、間違った掃除の習慣をなくすことです。一般的な掃除法の中には、ホコリを舞い上げたり、汚れを引き延ばしたり、空気を汚したりと、実は逆効果なものも多いんです。みなさんも、きれいにしようとして、無駄なことをし過ぎているかもしれませんよ。本当にきれいな状態を保つには、それぞれの汚れに合った方法で、ピンポイントに掃除していくのがベストです」
――一生懸命に掃除しても、逆効果だったらショックです。
松本「結果には必ず原因があるので、まずは、どうしてそこが汚れるのか、それはどんな汚れなのかを分析してみてください。それがわかれば、どんな掃除道具を使ってどう掃除すればいいのかが見えてくるはずです。
掃除って、物理と化学なんですよ。ホコリが部屋の隅に溜まるのは、人の動きで室内の空気が動いてホコリが運ばれるという流体力学。汚れを分解する洗剤は化学です。なので、そういった力をうまく利用すれば、無駄の省かれた楽な掃除で、確実にきれいを維持できます」
――『図解 健康になりたければ家の掃除を変えなさい』でも、“おばあちゃんの知恵”的掃除術や、小学校の掃除法はよくないと書かれていました。ナゼいけないのでしょうか?
 松本「“おばあちゃんの知恵”的掃除術に関しては、昔と今で住宅事情が大きく変わっているので、昔は良かったことが現代では逆効果になる場合もあるということです。たとえば畳にお茶殻をまいてホウキで掃く方法は、気密性の高い住宅が増えた現代だと、カビやダニの餌になるリスクの方が高いでしょう。
小学校の掃除法は、『窓を開けて、机と椅子を教室の片側に寄せて、濡れ雑巾で床を拭く』といったものですよね。この方法、空中にホコリを舞い上げて、床の水拭きで汚れを塗り広げているだけなので、病原体を含んだホコリなどを吸い込んでしまうリスクが高いんです。
掃除は見た目の“きれい”“汚い”ではなく、健康に過ごせる環境をつくるもの。食事や運動と同じです。そう考えれば、“正しい掃除”の方法もわかってくるのではないでしょうか」
松本「“おばあちゃんの知恵”的掃除術に関しては、昔と今で住宅事情が大きく変わっているので、昔は良かったことが現代では逆効果になる場合もあるということです。たとえば畳にお茶殻をまいてホウキで掃く方法は、気密性の高い住宅が増えた現代だと、カビやダニの餌になるリスクの方が高いでしょう。
小学校の掃除法は、『窓を開けて、机と椅子を教室の片側に寄せて、濡れ雑巾で床を拭く』といったものですよね。この方法、空中にホコリを舞い上げて、床の水拭きで汚れを塗り広げているだけなので、病原体を含んだホコリなどを吸い込んでしまうリスクが高いんです。
掃除は見た目の“きれい”“汚い”ではなく、健康に過ごせる環境をつくるもの。食事や運動と同じです。そう考えれば、“正しい掃除”の方法もわかってくるのではないでしょうか」
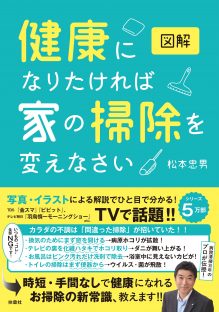 そこで、前回掃除の基本や大掃除のポイントについて語っていただいた、日本ヘルスケアクリーニング協会代表理事で、『図解 健康になりたければ家の掃除を変えなさい』(扶桑社)の著者でもある松本忠男さんに、きれいを維持する秘訣を伺いました。
そこで、前回掃除の基本や大掃除のポイントについて語っていただいた、日本ヘルスケアクリーニング協会代表理事で、『図解 健康になりたければ家の掃除を変えなさい』(扶桑社)の著者でもある松本忠男さんに、きれいを維持する秘訣を伺いました。
逆効果の掃除で、汚れを広げているかも!?
 松本「“おばあちゃんの知恵”的掃除術に関しては、昔と今で住宅事情が大きく変わっているので、昔は良かったことが現代では逆効果になる場合もあるということです。たとえば畳にお茶殻をまいてホウキで掃く方法は、気密性の高い住宅が増えた現代だと、カビやダニの餌になるリスクの方が高いでしょう。
小学校の掃除法は、『窓を開けて、机と椅子を教室の片側に寄せて、濡れ雑巾で床を拭く』といったものですよね。この方法、空中にホコリを舞い上げて、床の水拭きで汚れを塗り広げているだけなので、病原体を含んだホコリなどを吸い込んでしまうリスクが高いんです。
掃除は見た目の“きれい”“汚い”ではなく、健康に過ごせる環境をつくるもの。食事や運動と同じです。そう考えれば、“正しい掃除”の方法もわかってくるのではないでしょうか」
松本「“おばあちゃんの知恵”的掃除術に関しては、昔と今で住宅事情が大きく変わっているので、昔は良かったことが現代では逆効果になる場合もあるということです。たとえば畳にお茶殻をまいてホウキで掃く方法は、気密性の高い住宅が増えた現代だと、カビやダニの餌になるリスクの方が高いでしょう。
小学校の掃除法は、『窓を開けて、机と椅子を教室の片側に寄せて、濡れ雑巾で床を拭く』といったものですよね。この方法、空中にホコリを舞い上げて、床の水拭きで汚れを塗り広げているだけなので、病原体を含んだホコリなどを吸い込んでしまうリスクが高いんです。
掃除は見た目の“きれい”“汚い”ではなく、健康に過ごせる環境をつくるもの。食事や運動と同じです。そう考えれば、“正しい掃除”の方法もわかってくるのではないでしょうか」
1
2









